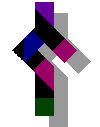
Welcome to Department of Cognitive Science Homepage
名古屋大学大学院
情報学研究科/心理・認知科学専攻
認知科学講座
updated: '25/06/27
研究分野
認知科学・計算機科学・言語科学などの手法と知見を基礎として,情報の理解と表出,並びに記憶や思考における知識表現とその理解・遂行に関する問題を中心に,情報処理の観点から広く人間の認知活動に関わる精神活動の解明を目指しています。
認知科学講座への配属を希望する人へ
情報学研究科心理・認知科学科学専攻を受験し,認知科学講座への配属を希望する者は,以下を参照の上,準備に努めて下さい。
- 「基礎」に関しては,心理・発達,感覚過程,知覚,学習と条件づけ,記憶,言語と思考,
知能に関わる内容について試問する。 以下が参考書である。 - ヒルガードの心理学(第15 or 16版),金剛出版
[AMAZON site] - Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology 15/E or 16/E
- 「論述」に関しては,それぞれの専門領域に関するより個別的な内容について試問する。
以下の研究科ホームページで提供されている情報も参考のこと。
[HERE]
スタッフ
■教授
三輪和久(MIWA, Kazuhisa)

情報処理アプローチに基づき,人間の高次思考過程を研究しています。 特に,科学的発見,より一般的には創造的思考過程に興味があります.また,学習科学や情報システム学との橋渡しを意識しながら,発見や創造の領域における学習支援や発想支援のための計算機システムや授業プログラムを開発しています。現在取り組んでいるトピックスには,発見,創造性,協同,洞察,類推,協同,外的資源,探索等があります。研究室では,理系/文系,心理学/工学の枠組みを超えて,異なるバックグランドを持った大学院生が,共存共栄しながら最先端の研究に従事しています。
■教授
川合伸幸(KAWAI, Nobuyuki)

ヒトはどのように賢いのか、またどうして賢いのか?ということに関心があります。直接、ヒトの知性の謎に迫るのではなく、サルやチンパンジー、その他の動物やヒトの子どもを対象に、ヒトの心の輪郭、あるいはヒトの知性の独自性を探るべく研究しています。現在取り組んでいるトピックスには、学習、記憶、行動の計画、運動学習、注意、視線への注意、自閉症者の注意、比較認知、動物の知性等があります。
■准教授
孟憲巍 (Xianwei,
Meng)